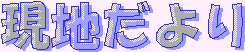思わず手をだす、身をのりだす 東京バザール
大会をハンズ・オンの場所にしよう
埼玉新英研 浅川和也
阿原成光・東京大会現地実行委員長は、寅さんにぞっこん惚れ込んでいるそうです。寅さんといえば、絶妙の語りで客をひきこむ実演販売の達人ですね。屋台はかけあいの場、実践者とビジターとのかけあいの空間。「これ、アルファベットカード」「こうして生徒に配って」「秘訣はね…、来た人だけにおしえましょう」…、実演販売ならぬ屋台が「新英研大会」に登場します。

実は、これまで東京新英研の春の研究集会では、会場のまわりにぐるりと書店や屋台(ブース)のある会場づくりがなされていました。そして展示のみでなく、昼食時にはそれぞれ参加者が屋台で教材や実践のトークを聞くというやり方が編みだされています。今回の東京バザールはその進化形です。

実は、これまで東京新英研の春の研究集会では、会場のまわりにぐるりと書店や屋台(ブース)のある会場づくりがなされていました。そして展示のみでなく、昼食時にはそれぞれ参加者が屋台で教材や実践のトークを聞くというやり方が編みだされています。今回の東京バザールはその進化形です。
インタラクティブな場づくり
海外の環境教育学会では「ハンズ・オン(Hands-on)」がワークショップをしのぐ勢いでした。もともとは博物館などで展示を見るだけではなくて、さわったり、身体を動かして、ビジターが主人公になって参加し、体験して学ぶ、という方法のことをいうようです。東京バザールでは、ハンズ・オンつまり、実践者とのインタラクティブな場を実現します。大会後も地域やサークルでの交流がさらに続けば、素敵ですね。初参加のみなさん、地域の支部・サークルの屋台からネットワークが広がりますよ。
2つのゾーンとカフェ:交流タイム
 受付のある1号館ロビーは書店などのAゾーン、地下はBゾーンとしてサークル・支部・ブロック会員やNGO団体などによるブースとカフェ。
受付のある1号館ロビーは書店などのAゾーン、地下はBゾーンとしてサークル・支部・ブロック会員やNGO団体などによるブースとカフェ。 ハイライトは8月2日(日)昼におこなわれる実践者ライブ・交流タイムです。交流タイムは分科会などでは得られない濃い時間になるでしょう。
Aゾーン
新英研会員の執筆による書籍を多くてがけている三友社出版が大会記念価格で出店します。また目利きによる選書で、これはという本を揃えた新吉祥寺書店さんが待っています。他教材販売も。
Bゾーン
 新英研の支部やブロック、サークル会員がオリジナル教材を持ち寄ります。例えば、東京からは東京大空襲の英文教材、評価やテストが文法項目別に提示されている実践集『みとめる わかる 花ひらく』や荒木好枝さんの英語通信『友&愛』をはじめ、教室ですぐに使える教材、グッズなどが並ぶ予定です。
新英研の支部やブロック、サークル会員がオリジナル教材を持ち寄ります。例えば、東京からは東京大空襲の英文教材、評価やテストが文法項目別に提示されている実践集『みとめる わかる 花ひらく』や荒木好枝さんの英語通信『友&愛』をはじめ、教室ですぐに使える教材、グッズなどが並ぶ予定です。
東京新英研春の研究集会で恒例の福袋の登場もあるかもしれません。国際機関や教科書にとりあげられている国々の大使館・政府観光局から提供されたパンフレットなども展示します。
フェアトレードのコーヒー・紅茶、クラフト販売のカフェも楽しみです。
<< PREV 0 1 2 3 4 5 6 7 8 NEXT >>
このページは、雑誌「新英語教育 2009年7月号」の「現地だより」から、転載をしたものです。